「今もゆれている」展
横浜市民ギャラリーあざみ野で、「今もゆれている」展が始まり、9月29日にトークをおこないました。
拙いトークで、十分に伝えられなかったかも知れません。いや、伝わらなかったと思います。
話したつもりでいること、話したかったことを事後的にまとめて、ここに紹介します。
まず、準備風景です。


デザインは、重実生哉さん
一階の、西村有さんの展示

石垣克子さんの展示

山城智佳子さんの映像作品

二階の今井智己さんの展示

拙作の展示

「地名」について
「地名」は、「自然史」に先立つシリーズで、「自然史」と密接な関係にあります。
アラン・トラクテンバーグは『アメリカ写真を読む』において、フロンティアの地の名付けは、合衆国政府によって組織された踏査隊の統括者、クレメンテ・キングの行為に特徴が反映されているとされていると記しています。キングは自らが踏査NO過程で「発見」した三つの湖に、幼い妹とその友達二人の名に因んで命名し、そして自ら撮った写真と自作の詩で構成した本を作り、妹たちに贈るという行為を、少女たちへの愛を込めて行うのです。
合衆国の地名に先住民の言葉が使用された事例は多く確認されているが、先住民の地名そのものが継承された形跡はないように思えます。もちろんここで断定的なことは言えませんが、北海道大学での講演の際に行ったジェイムズ・クリフォード博士への質問では確認されませんでした。質問は通訳の女性を介して行ったのですが、彼女は私の質問の意図を正確に理解した上で通訳してくれました。
大枠では、合衆国の地名は、先住民の地名を継承してはいないようです。これに対し北海道では、現在使用されている地名の80パーセントがアイヌの名付けた地名を起源としていると言われています。
なぜ、北海道ではアイヌの地名が継承されていったのか、そしてこの過程に何があったのか、そういったことの検証は、重要な問題を含んでいるように思えます。申し添えれば、合衆国の命名行為は暴力的で、北海道ではそうではないと言いたいわけでは決してありません。しかし、この差異を検証することには、十分な意味があるように思えるのです。
継承されたアイヌ語地名の「成立過程にある何か」、この「何か」に写真は接近できるだろうか。その可能性は、現代写真(現在撮影されている写真という意味で使用しています)よりも、過去の写真の検証により多くあるように思われます。例えば、現在「長万部写真道場研究会」という名の同人組織で研究とアーカイヴ作業を進めている、掛川源一郎の写真や、彼の同時代で交流もあった、長万部の写真同好会、「長万部写真道場」の写真を挙げておきます。彼らの写真は、方法の希薄な、経験的で、あるいは無意識性の優った「アマチュアリズム的」ともいえるのではないかと思います。しかしこれらの特徴は、否定的なことではなく、現代写真が生き延びるとすれば、こういった写真から何かを借用しなければならないとも思います。
ここで、山田秀三と知里真志保の地名研究の態度に注目したいと思います。
小安(「おやす」と読みます)という地名を、明治期の地名研究家永田方正は「川尻の漁場」と訳しますが、山田は、o-ya-us-i「川尻に・網が・ある・もの」と訳します。言語学の時代的な制約は当然であり、永田が不誠実だというわけではありませんが、山田や知里の翻訳における態度は、誤訳を避けるための、誠実なぎこちなさという身振りだと、私には見えます。地名の漢字表記は究極の、しかも意図的な、誤訳であろうと思います(「地名」の、初めての個展の際に、倉石信乃さんから寄せられたテクストのタイトルは、「誤訳の領土」であり、写真集「地名」にも掲載されています)。
「地名」における滑らかさを欠いたパノラマは、山田や知里のぎこちない翻訳の身振りの、せめてもの模倣なのです。
「地名」の写真で示した風景は、ある地名で名指されている場所であるという以外に、なんの美的な、または美学的な、あるいは撮影者としての主体的な前提がある訳ではなく、同じ方法で撮られてさえいれば、誰によって撮られていても、どの場所であっても、どの視点で撮られていても、そこに優劣の生じない、換置可能なものです。そのように、写真を曖昧な位置に置くこと、しかしそれは決して否定的なことではないと考えています。
「自然史」に移ります。
今回の展示は、「自然史」の、福島原発事故被災地から15点を選びました。
私たちは、台風21号と高潮の結果生じた「関西国際空港」の機能不全と「大都市のシステムの」内部での孤島化、北海道での胆振東部地震による山崩れとブラック・アウトという事態をほぼ同時に体験したばかりです。
ですが、土砂に生活の場と肉親や知人を奪われた人たちを除き、私たちは今だに、近代が生み出した文明にどこかで頼りきっていると思われます。「自然」によって破壊されたものは、近代の技術によって、いずれ修復されると思っていて、そして、現実にとりあえずは修復されてもいます。
しかしどこかで私たちは、作っては壊され、壊されては作るその果てしない循環に、恐怖と絶望を覚え始めているのではないでしょうか。
福島原発事故で生じた放射線物質の飛散と原子炉のメルトダウンという事態はどうか。修復可能なのだろうか。地震によって生じた土砂崩れとプルトニウムの飛散はどこが同じで、どこが違うのか。地震と津波で破壊された原子力発電所と台風による波で生じたタンカーと連絡橋の激突とは、どこが同じでどこが違うのか。プルトニウムとは果たして人工物なのか。「自然物」と「人工物」の境界は明確なのか。こういった疑問から「自然史」をスタートしました。もちろん写真で解答を得られるとは思っていません。ただ、少なくとも、すでに私たちは自然を、括弧付きの「自然」としか語り得ないという事態は指し示せるだろう思います。
飛散し、堆積した放射線物質の量によって設けられたとされる「帰還困難区域」は、地図上では明確に示すことができます。それは場所としても存在して、肉眼で見ることも写真に撮ることもできます。しかし、その境界に立ち、その内側に向かって写真を撮っても、放射性物質は写りません。当然のことです。写真が示すことは、「見えない」ということのみです。写真は「ここには実は見えない放射性物質が存在している」といったメッセージは示し得ません。
近年話題になっている「人新世」という概念にも関わっている哲学者のティモシー・モートンは、エルニーニョやラニーニャという現象は、数値化することはできるし、地図を作成もできる。そしてそれが引き起こす天候は直接に感知できると言います。エルニーニョはあるのだが見ることはできないということを言っているのだと思います。
ちょっと考えれば、この世界や社会には、あるのだが見えないことが山ほどありそうです。いわゆる先進国といわれている国々で、普通に考えて、一般の人々の多数に支持されることなどあり得ないないと思える政権が、一向に崩壊しないで継続するという事態を支えている力なども、その類かと思われます。
写真はこういった存在に対し、対抗的に機能することができるのだろうか。
これから先は個人的な妄想に限りなく接近しますが、
今かろうじて言えることは、エルニーニョのようなものがもたらした現象の断片を、シンボル化、あるいは提喩化しないように気をつけながら撮影する、ということのみです。シンボル化、あるいは提喩化しないように気をつけながら撮影する、ということは、先に触れた「長万部写真道場」のようなアマチュアリズム的な態度に通底しているようにも思われます。こういうとわずかにですが、方法ということに近づいた気がします。そのときに撮影者は、写真家と呼ばれもする積極的な主体ではなく、むしろ解体に向かっている「個」といった存在であったり、その集団であったりするのではないかと思っています。
そこで生み出される写真は、記憶から想起へといった回路からは溢れてしまう、撮影された事態を、曖昧なままに、しかし生々しい現在として現前させるものとしての写真であるかもしれない、と思っています。
あざみ野でのトークに先立つ28日、一橋大学の鵜飼晢ゼミに、倉石信乃さんと参加しました。
あざみ野でのトークと重なることを話したので、合わせて紹介します。
鵜飼さんの研究室のドアです。「今もゆれている」のチラシを貼ってくれました。

そのドアの裏には、
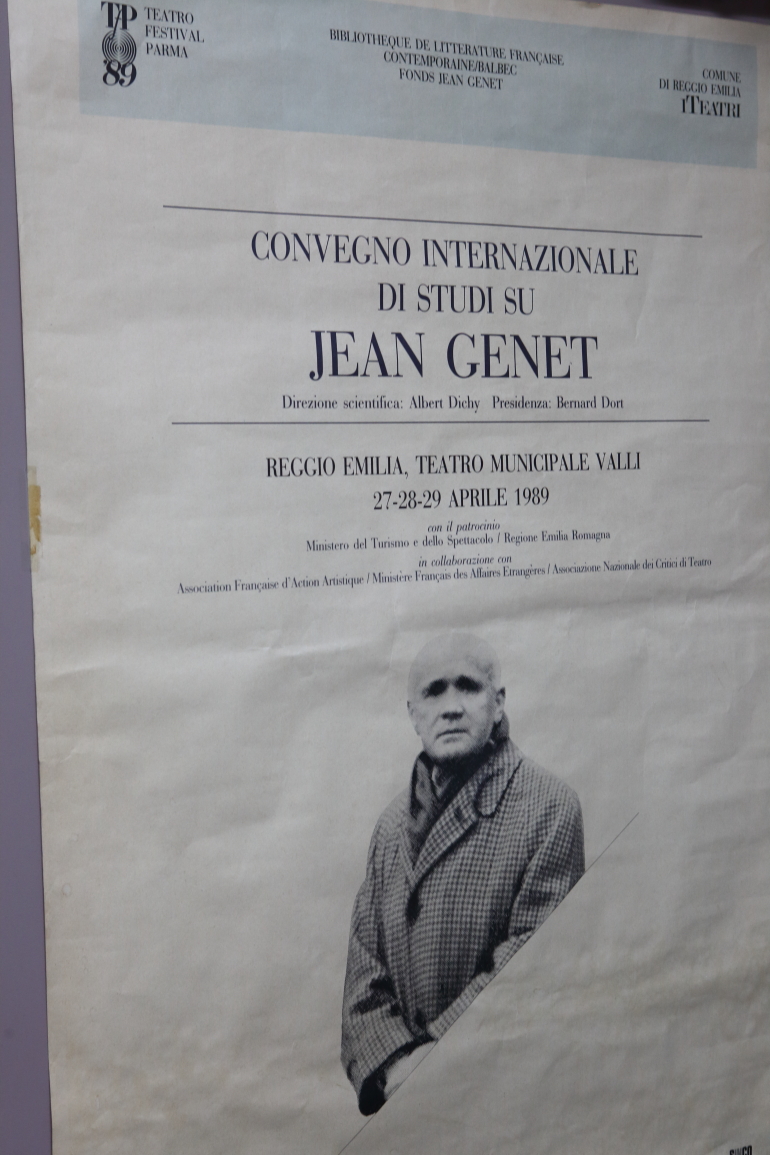
ゼミの様子。

